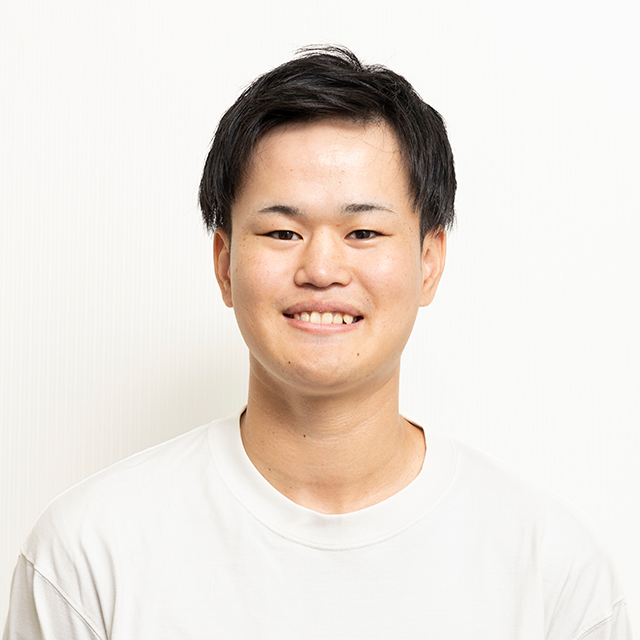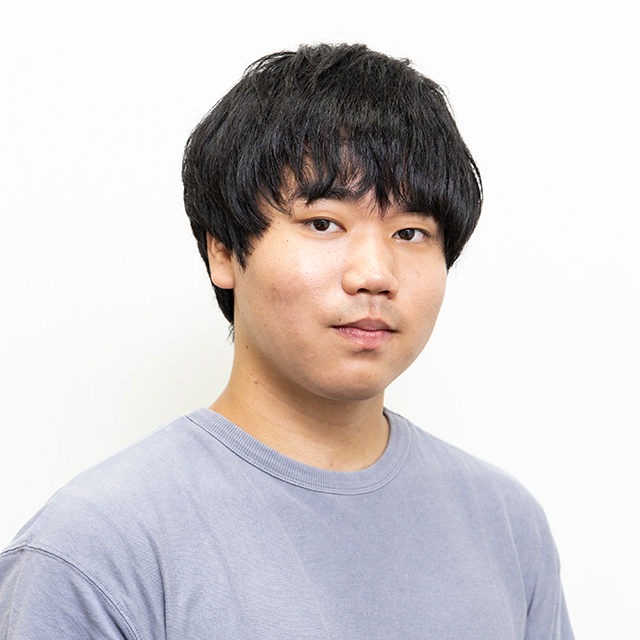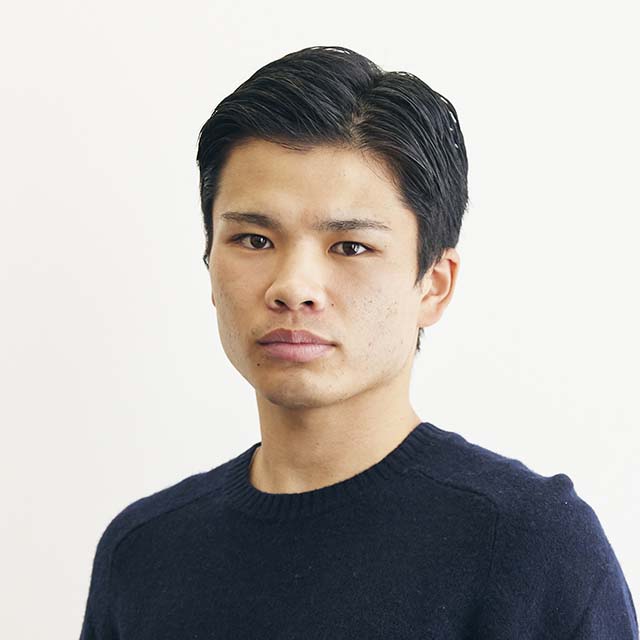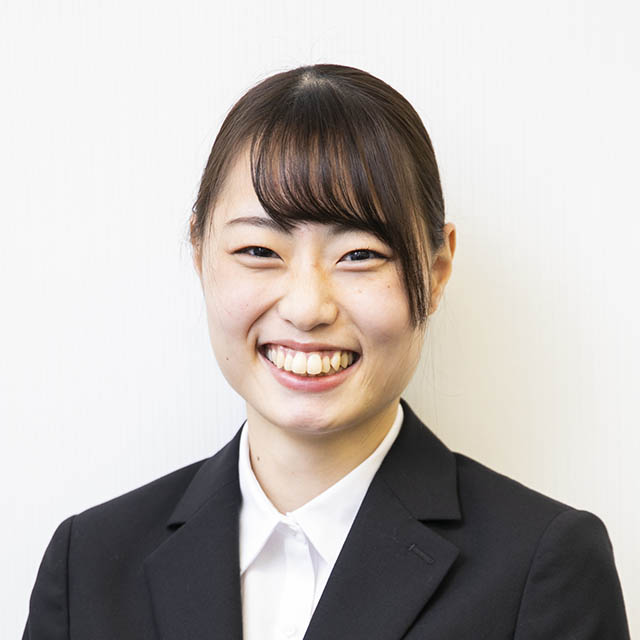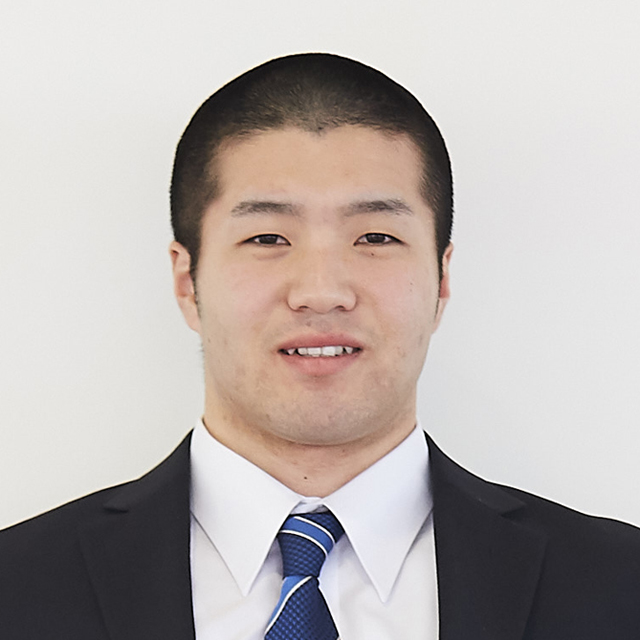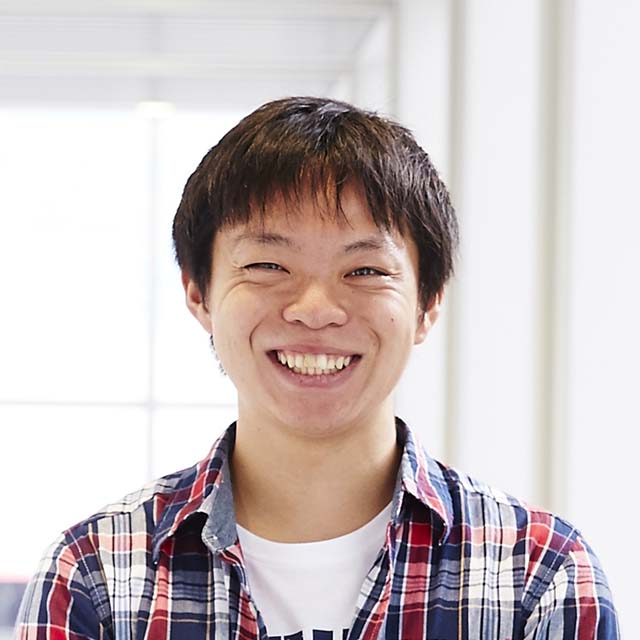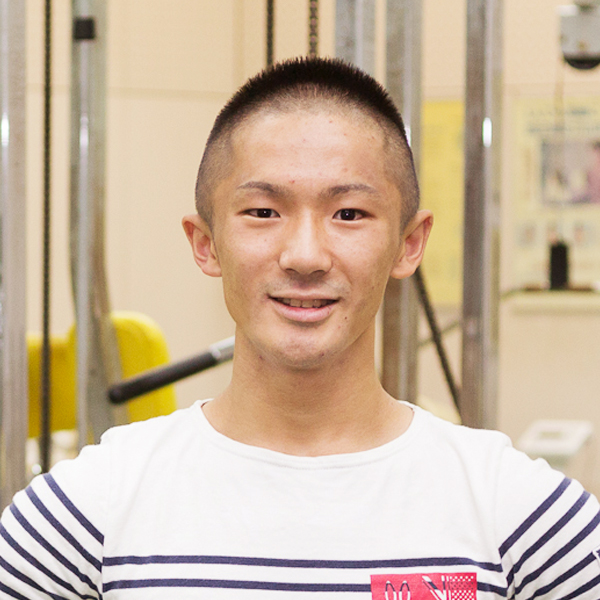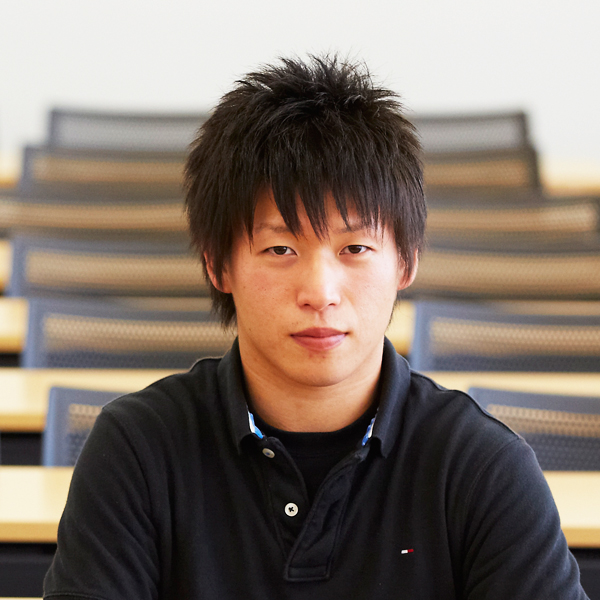大学生活ではどのようなことに力を入れましたか?

一番頑張ったことは資格の勉強です。高校時代はバスケットボール部に所属し、練習漬けの毎日だったので、大学では将来に向けた勉強がしたいと考えていました。選んだのは、日商簿記検定と宅地建物取引士。日商簿記は、入学当初から視野に入れていた公務員試験でも必要な数学への苦手意識を克服したかったこと、宅地建物取引士は不動産の仕事にも興味を持っていたので勉強を始めました。日商簿記検定は基本的には独学で、CPA会計学院が運営する「CPAラーニング」というサイトを活用することで2級まで合格できました。宅地建物取引士も最初は独学でしたが、1度目の挑戦で対策不足を痛感する結果となり、経法大の資格講座を受講することにしました。特に民法の分野に苦戦していたので、「迷惑かな?」と感じる程、何度も先生に質問に行きましたが、とてもわかりやすく教えていただいたおかげで点数を伸ばせました。一人だとついさぼってしまいますが、ペースメーカーのように自分を引っぱってくれる点も、資格講座を受けるメリットだと思います。
PBL(課題解決型学習)にも参加されていますね。
キャリアセンターから案内をいただいたことがきっかけで、参加することにしました。参加したプログラムは、地元のコミュニティFMラジオ局で、プロの方々と一緒にラジオ番組を制作する内容でした。企画内容の立案やインタビューを実施する企業や団体の選定、出演依頼の際に使用する資料の作成といった個々の仕事はもちろん、社会人の方と一緒に仕事をすること自体も初めてだったので、たくさんの刺激を受けました。
「勉強を継続することは難しい」という大学生の実感を基に企画テーマを考え、ある企業に所属する野球選手に、「何かを継続すること」についてインタビューすることになりました。一つのスポーツを継続されてきたアスリートのお話はとても刺激的で、特に「好きだからこそ継続できる」という言葉が印象に残りました。自分が頑張ってきた資格の勉強も、単に苦しいだけなら途中であきらめていたかもしれません。最初は何から始めていいのか分かりませんでしたが、継続していくうちに楽しさや面白さを感じるようになり、合格できたと思います。就活も含め「何かを継続する」「成果が出るまで頑張る力」は、大学生になって一番成長した力だと思います。
大学生活で印象に残っていることも教えてください。

たくさんの友人に恵まれたことです。高校までは「部活がすべて」だったので「趣味=スポーツ」という固定観念を持っていたのですが、大学で新しい友人と出会い価値観が変わりました。音楽フェスやライブイベントに参加するようになったのも、大学の友人に誘われたことがきっかけです。ボウリングも大学の友人と一緒に熱中しました。色々な人に出会えたおかげで視野が広がり、行動範囲も広がったと思います。
印象に刻まれた授業もありました。例えば「キャリア開発」「キャリアデザイン」「キャリア演習」といった科目では、多くのことを学びました。より良いキャリアを築くために必要なことはもちろん、実際の採用試験で求められる自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)をブラッシュアップしたり、面接のトレーニングをしたり、授業を通して就活の骨組みができたように思います。
さまざまな努力も実り、大阪府庁の採用試験に合格されました。志望のきっかけを教えてください。

子どもの頃から誰かの役に立つ仕事や、地域に貢献できる仕事につきたいと思っており、将来の進路として漠然と地方公務員をイメージするようになりました。市役所も受験しましたが、大阪府はより大きな区域に携わるため、事業の規模や予算も大きくなります。スケールの大きな仕事に挑戦したいと考えたことがきっかけです。
公務員採用試験合格に向けて、どのような準備をしましたか?
地方公務員だけでなく、民間企業もいくつか受けました。不動産関連の企業から内定をいただいた3年生の11月頃から、本格的な公務員対策を始めました。
基礎的な部分は、2年生の前期から受講していた「Sコース」で対策していたので、3年生の秋学期からはSPI(Synthetic Personality Inventory:総合適性検査)対策に力を入れました。内容としては参考書を繰り返し解くことが中心。さらに経法大独自のSPI対策教材である「経法SPI」サイトでは模擬テストに繰り返しチャレンジできるので、出題傾向やその時の自分の実力を把握しながら、弱点を潰していきました。対策を始めた頃に比べると解ける問題が増え、点数も大きく伸びていきました。また、大阪府庁採用試験のグループディスカッションは、「公務員特別演習」の授業で対策をする機会がありました。公務員採用試験ならではの進め方や特徴をふまえた実践的な授業のおかげで、苦手意識がなくなりました。
実は大阪府の最終試験の日程が他の市町村と重なっており、「保険がない」状態で挑んだので、合格した時は安堵感で一杯でした。合格の一報を受け取った時、偶然にも家族と大阪・関西万博の会場にいたので、会場から見ることができる大阪府庁の建物を眺めながら「春からはあそこに通うんだな」としみじみ思ったことを覚えています。
小論文対策にはAIも活用されたそうですね。
小論文対策を始めた当初は、過去問を自分で解いていくスタイルで進めていましたが、その方法で行き詰まった時に「面白そうだな」という軽い気持ちで試してみました。ネット検索で見つけた見本原稿を参考に、自分なりのテンプレートをつくり、それを応用して書いた論文を生成AIに添削させてみました。もちろん、AIの回答をうのみにするのではなく、サジェスト(検索エンジンが入力したキーワードに基づいて関連性の高い候補を提案する機能)してくれる修正点や文章表現を自分の言葉で修正したり改善したりするうちに、インプットが定着していったように思います。
キャリアセンターや公務就職支援室も活用されたそうですね。

キャリアセンターには面接試験前に頻繁に通い、対策をしていただきました。本番を想定した質問を投げかけていただき、しっかり応答する練習を重ねました。さらに公務就職支援室には、これまでの出題実績データが大量に蓄積されているので、その中から大阪府の採用試験の出題傾向に近い設問を選んでいただきました。事前に傾向をつかめたことが、自信につながったと思っています。公務就職支援室の職員の方には、民間企業・公務員を問わず、就活を円滑に進めていくためのポイントなどたくさんのアドバイスをいただきました。わからないところも気軽に質問できたので、とても心強く感じました。ここで受けられたサポートが、大阪府庁合格につながったと実感しています。
今後の抱負を教えてください
来年の春からは大阪府庁に勤めます。大阪はIR(Integrated Resort:統合型リゾート)事業やうめきた地区をはじめとする都市開発が進んでおり、他の自治体と比べ、先進性のある街だと思います。良い意味で変化し続ける大阪に、府職員として関われることをとても楽しみにしています。入庁後の配属はまだ決まっていませんが、大学で宅地建物取引士の資格を取得したので、その資格が活かせる都市計画や街づくりに関わりたいですね。
※掲載内容は取材当時のものです。